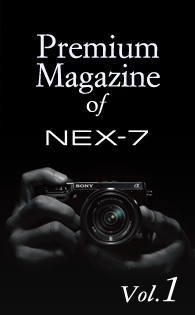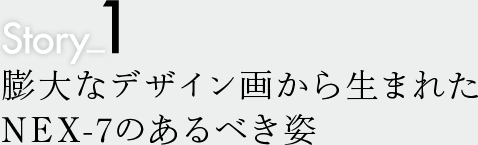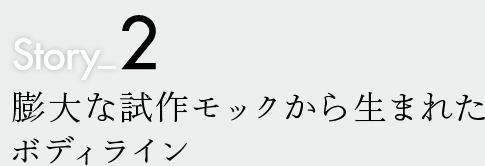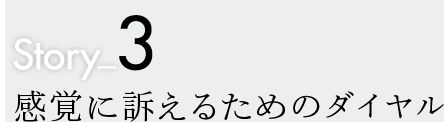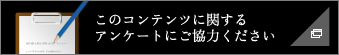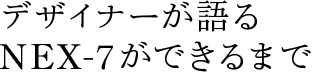
これまでに公開されているNEX-7の
コンテンツでは伝えていないものがある。
それはプロダクトが誕生するまでの、膨大に
描かれたスケッチやデザインモックだ。
残念ながら実物をお見せすることはできないが、
そのデザインの舞台裏を少しだけ垣間見せたい。

開発者への取材の場に行くと、NEX-7が誕生するまでに描かれた膨大なスケッチがあった。そのデザイン画をお見せすることはできないが、中にはこのNEX-7の完成型からは想像できないものもあった。デザイナーの高木は、初期のスケッチを見せながら話してくれた。「最初のデザインは実はシルバーだったんです。レンズと同じチタンカラーで、新しいカメラの登場感を新しいシルバーで提案できないかと考えていました。実際にシルバーメタリックの革をグリップに貼ったモックも作っています」。NEX-7は始めからブラックだったわけではなかったのだ。
 ソニー(株) クリエイティブセンター
ソニー(株) クリエイティブセンタープロデューサー/シニアデザイナー
高木 紀明
高木はさらにスケッチを進め、「トライダイヤルナビとして追加される2つのダイヤルをどうコントロールするか」を検証しはじめる。「当初はスマートアクセサリーシューを採用するつもりで、ファインダーも、さらにはフラッシュもなかったんです」。確かにスケッチには見たことのない上面液晶があり、ひとまわり大きなボディの光軸上にソニーロゴが置かれている。完成したNEX-7からはまったく想像つかないものだった。しかし、開発プロジェクトは急展開する。「ファインダーとフラッシュ、それからαシュー、この3つも入れてもっと小さくできないか」。ここから、デザイン画はNEX-7のあるべき姿に近づいていく。
 NEX-7の特長とも言えるファインダーと内蔵フラッシュ、αシューが開発初期の段階ではなかったというのは驚きだ。
NEX-7の特長とも言えるファインダーと内蔵フラッシュ、αシューが開発初期の段階ではなかったというのは驚きだ。
 この一直線に伸びる軍艦部分だけでも、かなりのモックアップを作ったそうだ。
この一直線に伸びる軍艦部分だけでも、かなりのモックアップを作ったそうだ。
「あまりに大量になってしまうので、少ししか持ってきてないんですけど」と言いながら、高木は何十ものモックを机の上に並べた。「『円筒と板』というNEXのコンセプトを検証するため、軍艦部分だけでバリエーションをいくつも作っています。軍艦をストレートに通したらどうなるか。シャッターボタンが置かれた傾斜面にアールでつなぐか、それともまっすぐ下ろすか。とにかくいっぱい作りましたね」。しかし今だから言うが、一見しただけでは素人にそのモックの違いはまったく分からなかった。
 RECキーもダイヤル操作の邪魔にならないよう、何度もモックで試しながら配置されている。
RECキーもダイヤル操作の邪魔にならないよう、何度もモックで試しながら配置されている。
「ボディが小さくなるにつれて、ボタンの置き場所がなくなってきて、最初フラット面に置いていたRECキーを斜めに置いたりしているんです。いろいろ精査していくと、そばに2つのダイヤルがあるので、そこに親指がかかってしまうためレイアウトできないとか」。デザインと操作性での検証を重ね、ほとんどすべての箇所でコンマ1ミリ刻みの格闘があったという。「NEX-7らしさを貫くために相当悩みましたね」。それらのモック群は、いまだに高木の机の脇に山積みされていると言う。NEX-7のボディライン一本に、デザイナーのこだわりがぎっしりと詰まっているのが伝わってきた。
 ボディラインの1本1本に、コンマ1ミリ刻みの格闘があり、
ボディラインの1本1本に、コンマ1ミリ刻みの格闘があり、デザイナーのこだわりが隠されている。
 精密機器のような操作感を生み出すために、細かなローレットがダイヤルに刻まれた。
精密機器のような操作感を生み出すために、細かなローレットがダイヤルに刻まれた。
「トライダイヤルナビのダイヤルも、最初はもっとカチッとした感じでクラシカルな雰囲気を出したりとか、回転するポジションごとにローレット(溝)を刻んでみたり。使い勝手を考えたときに、ストレートだとちょっと回しにくいかもしれないので、斜めのテーパーをつけて、円錐状にして指にやさしくしてみてはどうだろうかとか」。いろいろ試行錯誤を重ねるが、ある時ディレクターの新津が「見えないくらい細かいローレットはどうだろうか」と提案する。
 ディレクターの新津(写真左)から突然「見えないくらい細かいローレットにしよう」と言われて(笑)、と開発秘話を打ち明ける高木(写真右)
ディレクターの新津(写真左)から突然「見えないくらい細かいローレットにしよう」と言われて(笑)、と開発秘話を打ち明ける高木(写真右) ソニー(株) クリエイティブセンター
ソニー(株) クリエイティブセンターエグゼクティブアートディレクター
新津 琢也
「荒いローレットでは、従来の機器のつまみが入っているように見えてしまうんですね。やりたいのは、今までにない形状で印象に残るもの」。そこで高木は精密感のあるオーディオのダイヤルのようなものをイメージして、ローレットのピッチと角度をいろいろ検証する。「最初にできたものはヤスリみたいで爪が削れましたが(笑)。90度、120度、140度と微妙にローレットの角度を変えて、結果的にローレットの深さは8/100ミリ。ほとんど見えないくらいの溝なんですが、人間の指はそれを感じ取れるんです」。撮影者の感覚を徹底的に吟味することで、このダイヤルのローレット形状も生まれている。
 ソニー(株) クリエイティブセンター
ソニー(株) クリエイティブセンターシニアプロデューサー
高橋 正宏
何ひとつあきらめることなく、NEX-7らしさを貫いた結果として生まれた革新的なデザイン。その一方でクラシカルな雰囲気も漂う。そのことを聞くと「ファインダーの位置もそうですが、レンジファインダーを狙ったのではなくて、カメラの大きさが一番小さくなるように組み上げるための必然としてレイアウトしていきました。カメラの機能美が一番表れているところだと思います。ただのクラシカルな佇まいのカメラを求めるなら、軍艦をつけて、ボディに革を巻きつけて終わりです。でも、やっぱりソニーは古いものを追いかけても仕方ない。新しいものとしてここにある必然性がないとダメですね。NEX-7らしく。ソニーらしく。そうじゃないと何の意味もない」プロデューサーの高橋はそう話を締めくくった。