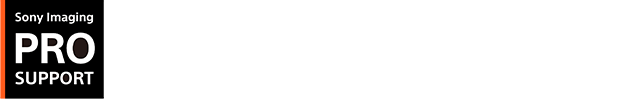三島有紀子監督がα7S IIIで描いた短編作品
『よろこびのうた Ode to Joy』に込める思い
~映画『DIVOC-12』撮影エピソード~
映画監督 三島 有紀子 氏
映像カメラマン 阿部 一孝 氏
『DIVOC-12』は、12人の映画監督が手掛けた12本の短編からなるオムニバス映画を制作するプロジェクト。今回はこのプロジェクトに深く関わり、物語のひとつを制作した三島有紀子監督と、三島作品のカメラマンを務めた阿部一孝氏にインタビュー。作品への思いや見どころ、撮影に使用した「α7S III」の魅力を伺いました。

三島有紀子/映画監督 18歳からインディーズ映画を撮り始め、大学卒業後NHKに入局。「NHKスペシャル」「ETV特集」、震災特集など市井の人々を追う人間ドキュメンタリーを数多く企画・監督。03年に劇映画を撮るために独立し、東映京都撮影所などでフリーの助監督として活動、NYでHBスタジオ講師陣のサマーワークショップを受ける。監督作『幼な子われらに生まれ/ Dear Etranger』(2017年)で、第41回モントリオール世界映画祭で審査員特別大賞、第41回山路ふみ子賞作品賞、第42回報知映画賞では監督賞などを多数受賞。最新作は『Red/Shape of Red』(2020年2月公開)。他の代表作として『しあわせのパン/ Bread of Happiness』(2012)、『繕い裁つ人/ A Stich of Life』(2015)、『少女/ Night's Tightrope』(2016)など。ドキュメンタリー作品から劇映画、テレビ作品まで一貫して、永続的な日常の中の人間にある軋みを描きつつも、最後には小さな"魂の救済"を描くことを信条としている。スタイルとしては、研ぎ澄まされた演出に下支えされた美しい映像作りに定評があり、一見すると柔らかい作風の初期作品から、ハードな演出が露出する近作まで、演出の姿勢は変わらない。

阿部一孝/映像カメラマン
東京ビジュアルアーツ映画科卒業。(株)ナックイメージテクノロジーでカメラを学びフリー撮影助手に。助手時代は柴崎幸三に師事し、平山秀幸、山崎貴監督作品などに数多く参加。
カメラマンとして『繕い裁つ人』、『ビブリア古書堂の事件手帖』など三島有紀子監督作品にも多数参加している。
不安と安心が交錯する世の中でも
「よろこび」を感じられる作品に
――『DIVOC-12』で短編作品を手がけることになった時の思いを聞かせてください。
三島監督 コロナ禍で撮影が延期や中止になり、いつ「クランクインです」という言葉が聞けるのかわからない、まるで砂漠の中に一人でぽつんと立っているような気持ちの中でこのプロジェクトに出会いました。私にとっては「砂漠に咲く小さなバラの花」のような存在で、その小さな花をこれからいかに大切に育てていけるか、ということに向き合っていた時間だったように思います。 プロジェクトに参加した他の監督たちも同じ心でいるのを実感しました。全員が、今この時代のこの状況の中で表現したいことは何か、自由に、本当に純粋に自分の作りたいものを見つめて形にしていく熱量を感じました。
――三島監督が描いた作品『よろこびのうた』のテーマやコンセプトは?
三島 昨年8月、日本で最初の緊急事態宣言が解除され、「時代はこれからどうなっていくんだろう」と漠然と思っていたころ、海が見たくなって千葉の九十九里浜に行ったのです。そこで今後のことをぼーっと考えていると、「不安」と「安心」という言葉が浮かび上がってきて、「不安というのは何だろう。その正体はなんなのか…その先に信じられるものってなんなのか?」たぐりよせたいと思いました。「それがきっと喜びと言われるものなんだろう」と思い、脚本を書き始めました。 ストーリーを作る上では、ある3つの出来事が軸になっています。ひとつは九十九里浜の砂浜で転んで倒れていた老齢の女性との出会い、ふたつ目は食堂で聞こえてきた会話。七十歳を超えた女性が「たとえコロナで生き残ったとしても100歳まで生きるとしたらあと30年生きなきゃならない。いったいどうやって生きていきゃいいのよ」と話していたこと。3つ目は人から聞いたインドでのボランティアの話。路上でもう命が危ないという方を見つけたら、息を引き取るまで抱っこしてあげるボランティアがあるらしいのです。この3つの出来事や情報が私の中で一つになって、「不安と恐怖の中での喜び」を形として提示したいと思って作ったのが今作『よろこびのうた』です。
富司純子さんの出演は私の作品だけでなく
プロジェクト全体にも大きな意味があった
――『よろこびのうた』は、年金生活の老婆・冬海役を富司純子さんが、冬海にアルバイト話をもちかける若い男性役に藤原季節さんが主要キャストとなっていますが、お二人にオファーした理由を教えてください。

三島 富司さんが出演した作品はたくさん観てきたので、私の中では「富司純子さん=映画」というくらいの大きな存在でした。ですから「いつかご一緒したい」とずっと思っていたのです。本作に登場する冬海は一人で孤独に生きているけれど、「助けてくれ」と誰かに寄りかかることのない、非常に気丈な女性です。強くて、人生を楽しむ欲もありながら、芯の部分では人間を慈しんでいる。そんな女性を誰に演じてほしいかと思った時、富司さんにお願いしたいと思いました。実際、本当に芯が揺るがない、人間としての核が動じない素晴らしい役者さんです。

一方、藤原季節さんは出演作品を観て「映画的な色気のある人だな」と感じていました。でも実際に会ってみると良い意味でイメージと違っていて「なんてカメラに愛されている人なんだろう」と感じたことを印象深く覚えています。作品への取り組みかたの話をした時、「この人だったら自分の恥ずかしい部分や、醜い部分まで、全部さらけ出して全身全霊で演じてくれるんだろうな」と思ったことが今回のオファーに繋がっています。
――お二人の演技から何か感じたことはありますか?
三島 富司さんは緊張感を与える人でありながら、それを和らげる母性みたいなものも持っています。自分自身が作り上げてきた芝居をただ投げるのではなく、藤原さんが演じられたお芝居をきちんと全部受けとめて返すような、包み込むような感覚がありました。これは藤原さんだけでなく、私たちスタッフみんなが感じたことだと思います。
――富司純子さんは、この作品にとって大きな存在だったのですね。
三島 私の作品だけでなく、『DIVOC-12』にとっても大きな存在でした。このプロジェクトで最初に出演のOKを出してくださったのが富司さんだったので。「誰が最初にOKを出してくださるか」はプロジェクトにとってとても大きな意味を持ちます。短編で、12人の監督で、となると受け取りかたもさまざまですし。でも富司さんは「この映画に自分が参加することで少しでも希望が生まれるのであれば」と言ってくださって。この時は本当に背筋が伸びました。 「コロナ禍をみんなで乗り切ろう」という時に、日本映画界でも大きな存在の富司さんが先陣を切って「希望を」と言ってくださったことはとても大きな意味があったと思います。
心の内を「色のない世界」で表現するため
細部までこだわった色
――作品を通してこだわった部分や注目してほしいシーンはありますか?
三島 こだわったものの一つは「色」です。人生の中で色が死ぬ時、色が生まれる瞬間というのがみなさんそれぞれにあると思うんです。私自身、コロナ禍で生きているのかも分からない感覚に襲われて、色のない砂漠の中に立たされていると感じた時がありましたから。そういった心の動きを追求したいと思っていたので、繊細なトーンまで色にはこだわりました。あとは「音」。音で今、何がなされているのか、何を考えているのかを表現している部分もあるので、音にも注目してもらえるとうれしいです。 シーンでいうと、やはりファーストカットでしょうか。作品としても非常に重要な部分であり、監督それぞれの思想が出る部分ですからね。本作は九十九里の海がファーストカットになりますが、この海を舞台に物語が始まっていくという、ある種の期待感というか高揚感を高める表現できるように映像と音を工夫しています。 冬海の部屋のシーンも、スタッフみんなでアイデアを出し合って決めたこだわりのシーンです。最終的には、1人の人間のプライベートを窓枠越しに覗き見る、という視点で撮ることになりました。こういう視点、私は結構好きなんです。
――目指す映像表現のために、カメラマンに伝えたことはありますか?
三島 元々モノクロで撮りたいと思っていたくらいなので、極力色を減らすようにお願いしました。全体的に「色の少ない世界」を表現したいと思っていたので、派手な色が入ってくる場合は少し色を抜いたりして。逆に心に色が付くようなシーンは、視覚的にも色を付けて、という感じに仕上げています。
階調表現の豊かさと高い機動性で
映画の世界へ踏み込んだ「α7S III」
――阿部さんは監督のリクエストに応えるべく撮影機材を選んだと思いますが、「α7S III」で撮影してみていかがでしたか?
阿部カメラマン 「色のない世界」を表現するにあたっては、「α7S III」の4:2:2 10bitによる豊かな階調が生きました。今回は空や海、砂浜など、単一の色の景色が多かったのですが、きれいにグラデーションが出ていたという印象です。特に海辺は重要なシーンが多かったので、単一な世界の中に質感を出し、要望された表現を作ることができたのではないかと思います。 三島 そうですね。空や海の印象を際立たせるためにも、きれいにグラデーションが出るかどうかは重要です。そういう意味ではかなり良かったと思います。 阿部 僕自身、映画の撮影では初めてミラーレス一眼を使ったのですが、「α7S III」はカラーサンプリングが4:2:2であることやS-Log撮影ができたりと、プロの世界に近い高画質の映像が撮れそうだなとかねてから使ってみたいと思っていました。ミラーレス一眼で撮影したものを劇場で観ることができるのは「ちょっとおもしろいな」と思う部分もありましたね。
――「α7S III」のようなミラーレス一眼を使うことでのメリットはありましたか?
阿部 やはり小型軽量ならではの機動性です。車の中で二人が会話するシーンでは車の窓に吸盤をつけて台を作り、そこにカメラを固定していました。大きいカメラではセッティングも大掛かりになりますが、「α7S III」はセッティングが楽で、その分多くのカットを撮ることができます。

軽くて手ブレ補正も効くので、手持ちでも積極的に撮影しました。ラストの大事なシーンではローアングルで被写体を追いかけながら撮影したのですが、重いカメラで撮るとなると相当大変です。それを、足場の悪い砂浜で身軽に手持ちで撮影できたことは大きなメリット。リテイクできる現場ではないためかなり助かりました。 三島 あれだけのローアングルで、手持ちで撮れるのですから「このサイズのカメラがあってありがとう」と思いました。
ズームレンズ1本で多くのシーンを撮影
ワンショットでは瞳AFも活用
――実際に「α7S III」で撮影して、便利だった機能はありますか?
阿部 高感度は噂通り、かなり良かったです。夜の電話ボックスを撮影するシーンでは少ない明かりでシーンに質感をもたらしてくれました。 事前に高感度の写り具合をテストしたのですが、ISO12800辺りからまた一段、画質のパフォーマンスが上がるんですよね。実際はそこまで上げずに済んだのですが、暗いところでもそこまで上げても大丈夫なんだ。という「奥の手」が残っていることは安心材料になります。 三島 このシーンは悪魔に魂を売るシーンでもあり、くっきりとした光と陰が必要でしたから、有り難かったですね。
――今回の撮影ではどのようなレンズを使ったのですか?
阿部 実はほとんどのシーンを「FE 24-70mm F2.8 GM」だけで撮影しています。24mmでも十分な広さがありますし、開放はF2.8ですがぼけ味が非常にきれい。普通はF2.8だと「もうちょっと開けてぼけ味を出したいな」と思うことが多いのですが、このレンズは予想以上にぼけがきれいなので、単玉を使うことはほぼありませんでした。

今回は砂浜での撮影が多かったので、砂が入り込まないようにレンズ交換にも気を遣うんですよね。レンズを交換すればフィルターも変えなければなりませんし、天気も変わりやすい状況でしたから、一台で臨機応変に対応できる優秀なズームレンズがあって本当に良かったです。 AFも活用しました。助手がタブレットからの遠隔操作でタッチフォーカスを使ってピントを合わせていたのですが、これがかなり便利。瞳AFを使えば素早く瞳にピントを合わせてくれますからね。ワンショットをただ追いかけるようなシーンに限定すれば、もうベテランの助手がフォーカスを送るくらい上手かったです(笑)。本当に、感心するほど上手にピントを合わせ続けてくれます。
グレーディングは東映デジタルセンターのスクリーンを使い
映画館と同じ環境で映像を調整
――グレーディングについて教えてください。
阿部 劇場で見る環境で色の確認ができるため、グレーディング作業は東映デジタルセンターで行いました。テレビのような光を放つモニターで調整する時と、スクリーンに映す時とでは輝度がまったく違うので、実際に映画館で観た時に「ちょっと違うな」と思うことがあります。でも東映デジタルセンターでは幅6mほどのスクリーンを使って映画館と同じような環境でグレーディングできます。「α7S III」で撮影した4:2:2の映像は映画環境にもフィットして、まったく違和感なく作業ができました。 三島 阿部さんはかなり早い段階でカメラテストをしてカラコレができていましたが、あれはどういう経緯で生まれたんですか? 阿部 衣装合わせの時にカメラを借りていたので、ご本人でカメラテストができたわけです。これを基に顔色を調整できましたからね。人それぞれに違うのですが、今回は富司さんに合わせた顔色のトーンに調整しました。モノクロっぽい作品になることを想定して、色ではなく明るさを少し変えて。そこから色を塗ってトーンを決めていった感じです。 三島 この作業が事前にできたことは、かなり重要でしたよね。 阿部 そうですね。大きいカメラだと準備が大掛かりですが、一眼カメラのα7S IIIはこのサイズ感なので、どこでも気軽にカメラテストができる。やはり、助監督など身近な人でテストをしてしまうと顔色が全然違うため本番で生かせないことも多いですから、この軽快さは良かったですね。 三島 本番でどういう肌色になるか、本番の衣装を着て、メイクしてカメラテストをできたのはとても大きかったと思います。この段階で多くの調整が済んでいたので、あとはこの色をベースに考えるだけ。そのためいろいろなことを効率よく、無駄なく、スピーディーにこなすことができました。 本作では、色の見え方が非常に重要です。共通の色を二人が持っていることで、二人が深層心理で繋がっていることを表現できますからね。具体的には藤原くんのマフラーに編み込まれているピンク色の毛糸と、富司さんの梅色の服がリンクするか、梅色がどんな風に見えるかがポイントでした。「α7S III」の機動力を生かして事前にカメラテストができたおかげで、こういった繊細な色も思い通りに表現することができたわけです。

12人の監督が大事に育てた花を鑑賞し、
みなさんの心にも小さな花を咲かせて欲しい
――出来上がった作品を観て、「α7S III」の映像表現はいかがでしたか?
三島 『よろこびのうた』は色の映画であり、色が非常に大事なポイントになりますので、空や海、砂浜のグラデーションをしっかり表現することができたのは大きな収穫でした。さらに車内の撮影など、大きなカメラでは大仰になってしまうようなシーンでも、楽にスピーディーに撮ることができる。色づくりと機動力は表現を生み出すことの助けになりました。
――映画公開を楽しみにしている読者の皆さんに、一言メッセージをお願いします。
藤原季節さんが「この作品には12個のまなざしがある」と言っていました。まさに私も、12人の監督が12のまなざしで映画を作ったと思っています。この世界はいろいろな見かたがあり「こんなに豊かなんだ」ということを受け取っていただき、「自分自身はこの世界をどう見たいのか」ということを探ってもらえたら、また豊かな時間が生まれるのではないかと思っています。 最初にお話した通り、このプロジェクトは小さなバラとなって私の目の前に現れてくれました。我々はそれを一生懸命育ててきましたので、作品を観たみなさんの心にも小さなお花のようなものが生まれるといいな、と思っています。ぜひ劇場でそれぞれの監督が育てた花をご覧いただければ嬉しいです。
『DIVOC-12』 10月1日より全国ロードショー
ワンクリックアンケートにご協力ください
αUniverseの公式Facebookページに「いいね!」をすると最新記事の情報を随時お知らせします。




![テレビ ブラビア®[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)
![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

















![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)






![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)






![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)


![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)







![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)
![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)