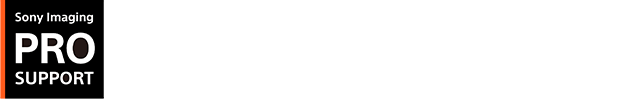交差する眼差し αが捉えた土地と人の関わり
写真家 山元彩香 氏
山元氏の作品が持つ独特の世界観。本インタビューでは、ジョージアを旅して撮られた写真を手掛かりに、それらの作品の魅力を紐解く。

山元彩香/写真家 1983年、兵庫県生まれ。京都精華大学芸術学部造形学科洋画コース卒業。2004年のサンフランシスコへの留学を機に写真の制作を始める。馴染みのない国や地域へ出かけ、そこで出会った少女たちを撮影することで、その身体に潜む土地の記憶と、身体というものの空虚さを写真にとどめようとする。2009年のフィンランド、エストニアでの撮影を皮切りに、エストニア(2010年)、ラトビア(2011、12、14年)、フランス(2012、13年)、ロシア(2014年)、ウクライナ(2015年)、北海道(2015年)、ブルガリア(2016年)、ルーマニア(2017年)、ベラルーシ(2018年)、マラウイ(2019年)、沖縄(2020,2021年)と各地で撮影を行ってきた。主なグループ展として「記憶は地に沁み、風を超え 日本の新進作家 vol.18」東京都写真美術館(東京、2021年)、主な個展として「 We are Made of Grass, Soil, Trees, and Flowers」Taka Ishii Gallery Photography/Film (東京、2021年)などが挙げられる。東欧やアフリカの各地で撮影を行い、国内外で写真展やレジデンスに参加。2019年に出版された写真集『We are Made of Grass, Soil, and Trees』(T&M Projects、2018年)でさがみはら写真新人奨励賞を受賞。東京都写真美術館(東京都)、清里フォトアートミュージアム(山梨県)、Villa Pérochon Centre d’Art Contemporain Photographique(二オール、フランス)に作品が収蔵されている。
文化が混ざり合う
魅力的な土地との出会い
――今回はソニーα7R IVを持ってジョージアで作品を撮られていました。ジョージアという場所を選んだ理由からお聞かせください。 以前からアルメニアの映画に興味があり、今までソニーで見せたシリーズの続きとして、同じコーカサス三国のジョージアという国に行ってみたかったんです。 映画で出てくる人物の風貌や、様々な地域の要素が入り混じった複雑な文化を面白いと感じていました。そんな時に、友人の画家が1年ジョージアに行くことになって。遊びにおいでと誘ってくれたので、そこで初めて訪れ3週間滞在しました。
――ジョージアは位置的にヨーロッパの文化と、ロシア系の文化が混ざり合うような場所なんでしょうか。 そうですね。ヨーロッパとロシアに隣接していて、かつては旧ソ連の構成共和国でした。西アジアとして区分されてもいますし、隣にはトルコもあります。色々な国に支配されてきて、その中でも自分たちの文化や言語を守り抜いてきた。面積は北海道くらいなんですが、一度外に出ても必ずみんなジョージアに戻ってくるというような、魅力のある場所です。
撮るものとしての自覚
感覚の変化が作品を変えた
――言語も分からない異国に行くというのは、当然文化も見えてくるものも違いますよね。それによって撮影に何か影響はありますか? やっぱり違う土地に行くと、色んなインスピレーションを受けますね。その時出会った知らない人を撮るというのは、自分にとっては新鮮なこと。 一方で、ずっと同じところで同じ人を撮っている写真家さんもいて、それは旅をして撮るだけでは到達できない何かがある気がする。その人について深く知らないまま一回で撮影を終えてしまうのは無責任というか、人間1人の奥にある深みを捉えきれていないのではないかとずっと葛藤がある部分でもあります。今回のジョージアでは、友達の知り合いの娘さんを何度も撮らせてもらったんですが、毎年撮りに行くとかそういうアプローチもあるなと思っています。
――この女性の写真ですね。こちらを向く女性の視線が印象的です。
これは、準備中に背景を確認するために何気なくカメラを向けて撮れたものですが、すごくいいものを残せたという実感がありました。いつもの自分が求めているものとは違うかもしれないのですが、眼差しの強さを感じて。普段は視線がないポートレートを撮ることが多いので、目が合うということに改めてどきっとしました。
――確かに山元さんの作品は被写体の方が直接目を向けず、どこかを向いて考えている雰囲気のものが多いですよね。 目が合うということは、撮影者を意識したものになるような気がして。私はカメラの存在を忘れるくらいになってほしかったので、目線ありの写真がほとんどなかったんだと思います。まだ言語化できていないんですが、何か繋がっている感覚に気がついてきた。今までは撮ってこなかったこういう作品を続けていくことによって、自分の中で言葉にできていくんだと思います。
――そういった感覚が芽生えたきっかけは何だと思われますか? 自分の変化に伴いゆるやかに変わってきたように思います。被写体になるモデルさんが自分の子どもでもおかしくない年齢になってきたことも心境の変化に影響しているのかもしれません。ここ数年で自分が置かれている状況が変わるのと同時に、手に取るものや撮りたいものも変わってきました。 ずっと同じことをやっていると慣れてしまう部分があるんですね。でも、それに慣れてはいけないんだと思わされる体験が旅行でモロッコに行った時にありました。地図にも出てこないような人里離れた小さな集落の宿に泊まったら、村で唯一のフランスから移住した宿の主人が昔フィルムカメラで広告写真を撮っていたらしく、私の持っているフイルムカメラを見て感動してくれて。仲の良い家族に撮影できるか聞いてくれたんです。その中で普段は顔見知りしか関わりがなく、海外の人に出会うのも初めてという少女がやりたいと言ってくれた。でも撮影をしているとどんどん顔が青くなって、そのうち座り込んで吐いてしまって。風邪などではなく写真を撮られるということに、本当に緊張してしまったんだと思います。 その経験で、やっぱりそれほどのことをやっているという自覚を改めて認識させられました。1人1人尊敬を持って向き合ってはいますが、写真を撮る・撮られるという関係性はそういうものなんだと。宿の主人は、狭いコミュニティの中で生きているから、これは彼女にとって社会に接続する機会だったと言ってくれて、ほとんど枚数としては撮れなかったんですが心に残る経験になりました。
裸足で土を踏みしめていたい
写真を始めた頃から続く意志
――撮影者としての自覚が芽生え、感覚も変化してきた。今は山元さんにとって1つの変革期というか、東京都写真美術館での展示※1や「Tokyo Gendai」※2などを経て、ステージも1つ上がり、多分ここからさらに熟していくんだろうなと改めて感じました。
※1:東京都写真美術館「記憶は地に沁み、風を越え 日本の新進作家 vol. 18」(2021) ※2:国際的なアートフェア「Tokyo Gendai」(2023)
――他の作品についてもお伺いします。この作品はどういったシーンで撮られたんですか?
廃墟は以前から変わらず撮るモチーフなんですが、知り合いの知っている村に連れて行って貰って、たまたまこの場所を見つけました。骨もそこの子供たちが拾ってきてくれて。ただ置いただけでも昔の静物画のように写ったりして、色々と即興で実験しながら撮っていきました。
町中では柘榴を見かけることが本当に多くて、あまり今までの旅では見なかったので気になりました。元々この地域に興味を持つきっかけになった映画が「ざくろの色」というもので、その中で潰した柘榴が布に染みていくシーンが印象的で。人の血や歴史など、様々なことを連想しながら撮影しました。
――これは先程の女性の後ろ姿でしょうか。 そうです。人を撮る時は、必ずぐるりと撮影するのを意識しています。後ろ姿だけを見ると、どこからか歌が聞こえて、何かこれから始まりそうな予感もしてくる。鼻歌をテーマにした映像も発表していますが、歌をテーマに今後も何が作れないだろうかと考えています。
――色々と発想されながら撮影しているんですね。大きな木の作品も複数ありました。
この木はすごく印象的で。背が高くて村中を歩いていても目につきました。細かい枝が密。集していて毛細血管のようで、人や生き物みたいに感じました。
――柘榴を血、木の枝を毛細血管のようと表現していましたが、山元さんの中で1つの土地が人間的なメタファーというか、そういう考えはあるんでしょうか。 そうですね。モロッコでも感じたんですが、人の肌の色がその土地の建築の壁やカーペットなどにリンクしていたりする。それはとても面白いと思います。 撮影場所として家屋と廃墟を選ぶのも、身体と同じものとして考えているからです。廃墟を、記憶や時間、全てを宿す入れ物だと捉えています。東欧に行き始めた時に特にそう思うようになったのですが、みんな壁紙を上から貼っていくので、壁がレイヤーになっていたんです。その廃墟に入り、ばっと破れているその下から何層もの重なりを目にした時に、その蓄積が身体の皮膚のようだと感じました。新しい場所というよりは、そういう誰かが住んでいた痕跡があるところに人間を置くというのが、自分の中では落ち着きます。
――その身体に対する感覚や落ち着くという意識は、何かご自身の境遇が原点にあったりするのでしょうか。 それはとてもあります。出身は兵庫県の田舎で、六甲山の裏にあり家の目の前は山でした。幼い頃から山や川を探検して高揚感を感じると同時に、1人で自然に入っていくと恐ろしさも感じました。その時の何か神聖な気持ちをよく思い出すんです。やっぱり人間の中には、どこに住んでいても自然に対する畏怖みたいなものがあるのかなと。そういうものを失いたくないし、取り戻したい。 私たちの世代くらいからテクノロジーがどんどんと進化してきて、「死」や色んな自然的なものが見えなくなっていると感じています。母からは幼い頃は庭で鳥を捌いて食べていたという話も聞きますし、全く体験してきたものが違う。「死」が隔てられているから、より恐怖を感じるし、この環境が人の心を苦しくさせているような気もします。それをどうにか楽にしたくて、役に立つのか分からないですが、写真がその何かになれたらいいと思っているんです。
――原体験として山や川などに入って未知のものに触れ、そこに本来の人間の生と死があるように感じてきたと。生きているという感覚とともに、そこで死ぬかもしれないというある種境界が曖昧なところがあって、それが自然であるのに今は見えなくなっているということですね。 豊かな自然は美しくもあり、恐ろしいものでもあって、幼い頃から自然と交わりながらもくっきりした境界があった。でも、それが私がよく撮影旅をしてきた東欧の田舎では全く感じないことに驚きました。子供達が遊ぼうって火を起こして焚き火をしだしたり、川や湖に躊躇なく裸で飛び込んだり。自然と友好的でありながら、ここには神様がいると知っているんですね。それが宗教としてではなく、当然のこととして存在している。 今はAIなども出てきて何事も便利な未来に進んできているのかもしれませんが、やっぱり裸足で土を踏みしめていきたい。自然に根付いている本来の感覚を忘れず、生きているという実感を得たいという思いがあります。これは多分、写真を始めた頃から無意識に思っていたことです。
――例えば探検をする時に調べていけば生存確率は上がって、最短ルートも分かる。でもそれと同時に失っていくものもある気がしますよね。普段廃墟に撮影で入る時には、事前にリサーチをせず、体ごと初めての情報としてぶつかっていくスタイルなんですか? 写真とリサーチは非常に相性がいいと思うんですが、私は先入観なしに見たいのでほとんど調べずに行き、現地の方からその土地の話を聞くようにしています。最初にアメリカに撮影に行った時に、自分の身体感覚が機能していないということに気付かされました。でも、感覚が目覚める場所に行けば、人間の身体はこんなに開かれるんだと実感して、その場での感受性を大事にしようと思ったんです。
デジタルとフィルムの両方が
作品づくりを助けてくれる
――山元さんの場合は感覚だけで撮っているというよりは、予期しない出会いとぶつかりながら作品をつくっているように思えます。写真が本来意図せぬものも含まれるという、その在り方に自らの身体を近づけていくというような。 今回の撮影では、α7R IVとDistagon T* FE 35mm F1.4 ZAを組み合わせていましたが、前回も同じようにされていましたよね。 そうですね。普段使っている中判フィルムカメラと近い感じで撮れるので安定の組み合わせです。自分の気に入った色に合わせやすくて、操作も複雑じゃない。シンプルに変えるくらいで綺麗な寒色、彩度が出る気がします。 細かいところでピシッとピントが素早く合うのでそれも助かっていて。オールドレンズと合わせた実験もしてみました。ロシアの古いレンズをアダプターでつけて撮ってみたら、色はソニーのままで、でもフィルムっぽく、そこまでシャープにならない絵が撮れたりして。
――いつもデジタルとフィルム、2台体制で持っていくんですか? そうですね。普段使っているフィルムカメラは、三脚に固定してからファインダーで覗きます。デジタルだとより気軽に色々と撮れて、自分の想像していないものを見ることができる。この構図や角度がいいんだと気づきやすいです。 固定したファインダーから見えるものがいい時もあれば、そこからでは見えない光がいいなと思うこともあるので、この2台体制が助かっています。デジタルとフィルム、2つが私の撮影には欠かせないものですね。
ワンクリックアンケートにご協力ください
αUniverseの公式Facebookページに「いいね!」をすると最新記事の情報を随時お知らせします。




![テレビ ブラビア®[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)
![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

















![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)






![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)






![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)


![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)







![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)
![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)