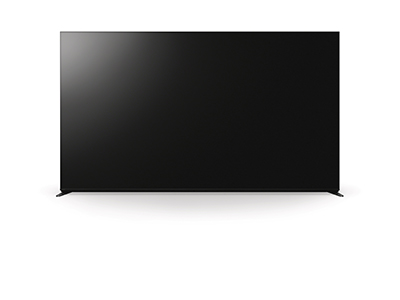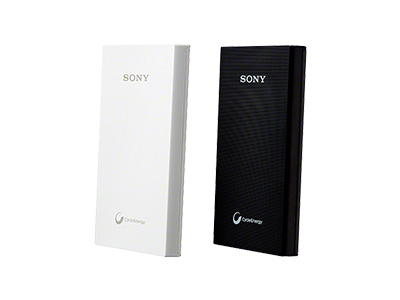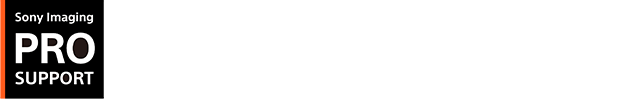鉄道絶景+α
第6回銚子電気鉄道(千葉県)
鉄道写真家 中井精也 氏
撮影日:2月14日 15時17分銚子電気鉄道(君ヶ浜〜犬吠)
青い海と銚子電鉄。これまでに何度も撮影していた場所だが、わずかに位置を変えて手前に森を入れると雰囲気ががらりと変わった。有効約5,010万画素の描写力が光る
新機材が写真の新たな可能性の扉を開く

千葉県の北東部、関東の最東端に位置する銚子市に、のんびりと走るローカル私鉄がある。銚子駅から外川駅までのわずか6.4kmを約20分かけて走る銚子電気鉄道、通称銚子電鉄だ。僕が初めてこの鉄道を訪ねたのは、中学1年生のとき。ずっと赤字続きで、いつ廃止になってもおかしくないといううわさを聞いて、いてもたってもいられずに出掛けた。駅ではたいやきに使う一斗缶を半分に切っただけのものをチリトリにし、それを100円で販売しているのを見て、電車を走らせるのは大変なんだなぁと、中学生ながら胸を痛めた。あれから45年。とっくに廃止になっているはずの銚子電鉄は、今日も元気に走り続けている。愛機α1 IIとともに、銚子電鉄の今を捉えた。銚子電鉄の魅力は、何と言っても昔と変わらない素朴な鉄道風景だ。とはいえ、路線の長さが6.4kmしかない沿線風景の中で、写真が撮れる場所は限られる。銚子電鉄は何度も通っているだけに、つい同じ構図をトレースしたくなる。だから今回は、新しい相棒であるα1 IIと、「ほんの少しでも変えてみる」ことをテーマに撮影した。定番である最初のページの「地球の丸く見える丘展望館」から望むカットも、ほんの少しだけ位置をずらすだけで、道路を手前の森で隠すことができた。目からウロコが落ちる思いだった。ずっと携帯の基地局に悩まされていたキャベツ畑の風景も、少し立ち位置を変えるだけで、すっきりとした写真に変化。いつもの踏切も夜に訪ねるとまったく違う雰囲気になっていた。最新の超望遠レンズを通して見た線路は、不思議とこれまでと違う景色を見せてくれた。新たなカメラやレンズとの出会いが、被写体への向き合い方を変え、新たな発見から表現につながっていくのだと、実感した旅になった。
撮影日:2月15日 8時24分銚子電気鉄道(観音〜本銚子)
新望遠レンズFE 400-800mm F6.3-8 G OSSで撮影。600mmを超える超望遠域だからこそできる圧縮感。まるで深い森を走るような、幻想的なシーンになった
撮影日:2月14日 9時36分
彩りのない冬も銚子電鉄沿線ではベストシーズンだ。広大なキャベツ畑が広がる定番ポイントだが、撮影位置をずらすことで、基地局のアンテナを入れずに撮影できた
撮影日:2月14日 19時00分銚子電気鉄道(海鹿島〜君ヶ浜)
キャベツ畑の中にポツンとある「19号踏切」。いつもは昼間に撮るが、夜はさらにロマンチックな雰囲気になる。右側にある幻想的な光筋は犬吠埼灯台の灯りだ
撮影日:2月14日 12時26分銚子電気鉄道(観音〜本銚子)
いつもは行かない森の中に分け入ってこちらも新たに加わったFE 16mm F1.8 Gで流し撮りをした。小型・軽量の新レンズは撮影のフットワークを軽やかにしてくれる。列車を画面の真ん中に配置し、周辺をレンズのパースで形が変化した木で埋め尽くした
<Pickup LENS>FE 400-800mm F6.3-8 G OSS

テレ端800mmという超望遠域をカバーするレンズが登場した。質量が約2.5kgと軽量だが、僕のスタイルである手持ち撮影ではやや重く感じる。インナーズームで、テレコンにも対応している。遠くの被写体を狙うときはフォーカスレンジリミッターで8m〜∞にすると快適に撮影できる。
<Photo Technique>星空撮影ではファインダーの明るさをオートに

夜間撮影は難しいイメージだが、僕は絞りを開放近く、露光は30秒にして試し撮りをしながら、ISO感度を決めていく感じだ。露出を決めるときに気を付けたいのがファインダーの見え具合。夜は明るく見えるため露出アンダーになりがちだ。ファインダーの明るさ設定を「オート」にして、少し明るいくらいの露出で撮るのがコツだ。
<絶景EPISODE>犬吠埼灯台と太平洋をバックに走る2000形
銚子電鉄沿線の最大の観光スポットである犬吠埼灯台。残念ながら列車からはチラッとしか見えないが、山に登ればバッチリ撮影できる。FE 70-200mm F2.8 GM OSS IIをクロップして300mm相当で撮影。有効約5,010万画素を誇るα1 IIなら、テレコンバーターを使用するよりもクロップの方がオススメだ。
記事で紹介された機能の詳細はこちら
記事で紹介された商品はこちら
ワンクリックアンケートにご協力ください
αUniverseの公式Facebookページに「いいね!」をすると最新記事の情報を随時お知らせします。