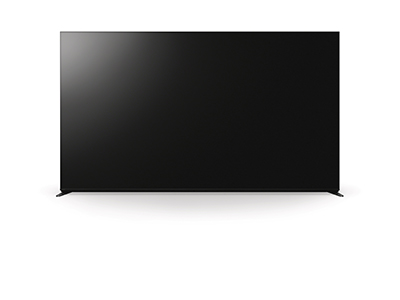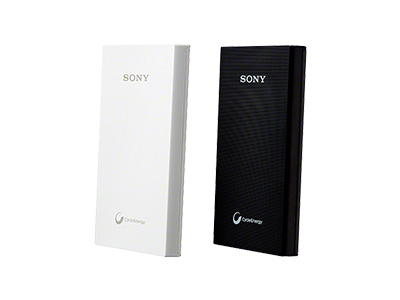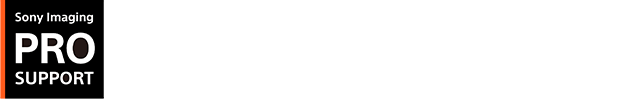CP+2025「α1 IIで映画を撮る 映画「SUNA」スチル&ムービーシューティング」
アーティスト・小説家・俳優 加藤シゲアキ 氏
写真家 末長真 氏
2025年5月より全国映画館にて上映となる短編映画制作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS Season7」内プログラムの1つである映画「SUNA」。NEWSのメンバーとして活動しながら、俳優や小説家としても活躍する加藤シゲアキ氏が監督を、フォトグラファー・末長真氏が撮影監督を務める本映画は、映画本編のムービー・スチル写真ともにソニーα1 IIで撮影された。ハイエンドモデルα1 IIはハードな現場でどう使われ、その実力を発揮したか。加藤氏・末長氏両名が登壇したCP+2025のステージでのトークを一部抜粋・編集して紹介する。

加藤シゲアキ / アーティスト・小説家・俳優 アーティスト・小説家・俳優。1987年生まれ、大阪府出身。青山学院大学法学部卒。NEWSのメンバーとして活動しながら、2012年1月に『ピンクとグレー』で作家デビュー。その後もアイドルと作家活動を両立させ、2021年『オルタネート』で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞。同作は直木賞候補にもなり話題を呼んだ。また『なれのはて』でも2作連続直木賞候補となった。他の小説作品に『閃光スクランブル』『Burn.―バーン―』『傘をもたない蟻たちは』『チュベローズで待ってる AGE22・AGE32』、エッセイ集などに『できることならスティードで』『1と0と加藤シゲアキ』、呼びかけ人として参加した能登半島地震支援チャリティ小説企画『あえのがたり』がある。2025年2月26日には最新長編小説『ミアキス・シンフォニー』が発売された。

末長真 / 写真家 写真家。1990年生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業後アマナを経て、2016年より瀧本幹也氏に師事。2021年独立。
加藤:映画「SUNA」は、短編映画制作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS」のために制作した作品です。砂に溺れた遺体をめぐる事件に刑事2人が向き合うというオカルトスリラー作品となっています。2025年5月9日から2週間、全国の映画館で上映され、その後順次配信となります。
――映画本編はソニーα1 IIと、同じくソニーのシネマカメラBURANOを使って撮影をされています。末長さん、この2台はどのように使い分けられましたか?末長:基本的にはBURANOをメインカメラとして、画作りで重要になるシーンや慎重にこだわりたいカットを撮っていきました。一方、BURANOを設置している時間や場所の余裕がない場合はα1 IIを手持ちで撮っていくスタイルに切り替えました。

左がα1 II、右がBURANOを構える末長氏。α1 IIでアングルを決めたあとBURANOを同位置に設置。

普段からαシリーズを使用している末長氏は、スチル撮影の延長のようにムービー撮影ができるため捗ったという。
――α1 IIが特に役に立ったシーンは?加藤:末長さんとは事前にロケハンに行ったものの、アクションシーンはやはり俳優ありきのものなので、事前に綿密なところまでは決めきれないんです。そして迎えた撮影本番、時間も押してきていた時に、α1 IIが役立ちました。シネマカメラに比べて圧倒的に軽量かつ手ブレ補正の効果もかなり強いので、手持ちならではの画作りも活かし、スピーディーな撮影に一役買ってくれました。8Kで撮れるので画質も担保されている安心感もありましたね。当初はBURANOをメインにα1 IIをバックアップ用として考えていたのですが、その役割が反転した瞬間が何度かありました。

コンパクトなボディに8.6K、35mmフルフレームイメージセンサーを搭載したシネマカメラBURANO。デュアル・ベースISOの採用で、暗い環境下でのシーンが多い本編でもノイズを限りなく抑えたクリアな画が得られた。スキントーンの美しさ、フルサイズセンサーを活かした立体感・密度感のある画は、ぜひ劇場の大スクリーンで体感してほしい。
末長:BURANOは撮影班の方がカメラを動かして僕はモニターで確認していることが多かったのですが、スケジュールやロケ地がかなりタイトだったこともあり、時間や場所的な余裕がない場合は現場で判断して僕自身が手持ちで回すことに切り替えられたことで、助かったシーンもかなりありましたね。加藤さんがこだわっていたアクションシーンも、α1 IIによる身軽な撮影体制のおかげでとても躍動感のあるシーンが生まれました。

――編集やカラーグレーディング時に、2台それぞれで撮った画に画質の差は感じられましたか。加藤:もちろん、細かい部分を観れば描写力の違いは感じられるのかもしれませんが、画質の差はまったく気にならなかったですね。とはいえBURANOの繊細な表現力は圧倒的で、用途によってこの2台を使い分けるという体制がぴったりハマりました。末長:カラリストの方も、それぞれの画のマッチングがまったく苦でなかったと言っていました。
――そんなハードなスケジュールの中で、さらに映画本編の撮影の合間にスチル写真も末長さんが撮影されています。末長さんは映画「怪物」などスチル写真も多く手掛けられているのですが、スチル写真を撮られる上で意識されていることはありますか?末長:スチル写真とは映画のポスターやWebサイトなどの広告物として使われる写真なのですが、それらを撮る上では、なるべく映画本編と同じ画角やライティングにならないように意識しています。同じにするのであれば映画の切り出しでもいいですからね。映画の世界観を伝えられるものであるという前提の上で、制約がないのがスチル写真の面白さだと思っています。
――こちらは監督兼主演も務められている加藤さんと、W主演である正門さんの2ショットですね。本編ではどういった状況のカットなのでしょうか。加藤:映画冒頭の事件現場ですね。ロケ地は生コンクリート工場で、タイトル通り「砂」を連想させる場所です。末長:照明部が作った空間のライティングのみで、2人に対して特別にスチル用のライトをあてているわけではありません。事件性が伝わる赤いライトと、砂を感じる背景で光の良い場所に立ってもらいました。レンズはFE 50mm F1.2 GMで、開放F1.2で撮っています。誰かにピントが合わなくなってしまうので、複数人のカットにおいて開放で撮ることは一般的にタブーとされています。仔細にみれば2人にピントは合っていないけれど、今回はぼけ感を重視して開放を選択しました。FE 50mm F1.2 GMは絞り開放でもかなりシャープな描写が得られるので、たとえば印刷物になった時にピントが外れていることを感じさせません。
――極限までぼけさせることで、より2人の表情に焦点を当てたということですね。さて、こちらのカットはいかがでしょうか?
加藤:これは事件の真相に迫るシーンで、室内プールで撮影しています。ぜひ映画を観てほしいのですが、プールならではの天井の高さや青みがかった色味が印象的な場面です。今回は映画本編もスチルも末長さんが撮影されているので、映画のカットとカットの合間にスチルを撮ることができて、スムーズでしたね。
――特に今回は、映画もスチルも同じα1 IIで撮られていたので、機材の入れ替えという点でもスムーズに行なえたのでしょうか?末長:そうですね。ここのシーンは映画でもα1 IIを使っていて、違うセットの準備をしている合間に同じ機材でシームレスにスチル撮影ができたのは大きいです。また、加藤さんもおっしゃっている通り、今回はどちらの撮影にも僕が関われたので、撮るべきポイントや、セットチェンジのタイミングが理解できているので、とても効率がよかったです。
――このカットのポイントは。末長:これも映画用の空間ライティングのみで、屋外から大きなライトを打っていますが、室内は薄明り程度のとても暗い空間でした。一方で余計なライトをあてても雰囲気を損ねてしまうので、2人の持つ懐中電灯の光をわざとレンズに入れてフレアを起こし、さらにレンズ表面の反射によるレフ板効果で顔を明るく持ち上げています。

加藤:これ、すごく難しい撮影でした。実際にはほぼ真っ暗で、懐中電灯と窓の明かりのみ。そんな状況下で、短時間でこのカットを切り取れたのは、末長さんのカメラやレンズ、ライトへの理解度、長年培われてきた判断力あってこそだと思います。懐中電灯の角度や位置も実はかなりシビアでした。まさに、それまで映画を回していたα1 IIだからこそ、スムーズにスチル撮影へ切り替えられたのだと思います。
――この1枚では、F値が0.95というオールドレンズを使われたそうですが、そのようにレンズ側に手ブレ補正機能がついていない場合でも、α1 IIのボディ内手ブレ補正機能が役立ちましたか?末長:本当にα1 IIの圧倒的なボディ内手ブレ補正機能には助けられました。手持ちで1/15秒〜1/30秒くらいのシャッタースピードに設定しても安心してシャッターが切れます。また、今回のように非常に暗いシーンでも優れた高感度耐性のおかげでディテールが損なわれていないのも驚きでした。加藤:撮影は、屋外のシーンは夜、室内でも薄暗いシーンが多かったのですが、それに対応してくれたソニー製のセンサーの力をまざまざと感じましたね。
――今回は、もともと写真がご趣味の1つであるという加藤さんにα1 IIで作品を撮ってきていただきました。
撮影;加藤シゲアキ
撮影;加藤シゲアキ
撮影;加藤シゲアキ
撮影;加藤シゲアキ
加藤:2025年の1月に、僕がファシリテーターを務めた音楽イベント「S-POP LIVE」からの4枚です。ちょうどカメラをお借りしていた時期でもあったので、せっかくなのでライブ撮影をしてみたいなと。僕も20年くらいカメラはやっているのですが、これほど高機能のカメラを使ったことがなくて、驚きました。特にポートレイトを撮る方には本当におすすめしたいですね。それはやっぱりオートフォーカスの性能の良さもそうですし、さっき末長さんもおっしゃっていたようにボディ内手ブレ補正機能のおかげで、気合を入れれば手持ちでも1/8秒でカメラブレは防げました。ライブフォトでは1/250秒くらいをベースにしていたので、1/8秒はありえない数字ですし、今まで見たことのない新しい表現が得られました。
――末長さんもスローシャッターで撮られることが多いと聞いたのですが、それが感情の動きを引き起こす写真の秘訣になるのでしょうか。末長:そうですね。僕も基本ブレるかブレないかのギリギリのシャッタースピードで撮ることが多いですね。「怪物」のポスターもすべて1/30秒や1/15秒で撮っています。よく見ると被写体ブレしているのですが、その感じがどことなくフィルムっぽくもあり、目を引く写真になるのだと思います。
――そういった表現にも、α1 IIの強いボディ内手ブレ補正機能が相当に役立っているのですね。そしてもう1枚、こちらは車のミラー越しの自撮りですね。
撮影;加藤シゲアキ
加藤:いろいろな風景や状況でα1 IIを試したのですが、オートフォーカスの性能を検証するために鏡越しに挑戦してみました。実はこういう鏡越しの写真って難しいと思っているのですが、シャープな描写、躍動感、そして何より車の車窓越しに撮っているのにもかかわらず僕の目にちゃんとフォーカスセンサーが反応していたことには感動しました。
――全体の質感もとてもきれいですよね。加藤:これも先ほどのライブ写真と同じく少し粒子を足しているのですが、元のデータはもっときれいでシャープな写真でした。レンズはFE 24-70mm F2.8 GM IIですね。
――FE 24-70mm F2.8 GM IIの描写はいかがでしたか?加藤:これまでほとんど単焦点レンズしか使ってこなかったのですが、このFE 24-70mm F2.8 GM IIで撮影した絵は、まるで単焦点レンズで切り取ったように美しい描写力でした。それはちょっと驚きでしたね。

――ズームレンズとして最高の誉め言葉ですね。それでは最後に末長さん、α1 IIを使われてみて、どういった現場で活躍すると感じられましたか。末長:α1 IIはスチルのクオリティはもちろんですが、動画撮影機能のスペックも高く、何より8Kが撮れるのは驚きです。CMやWebムービーの現場で使われることが増えていくんじゃないかなと思っています。今回の「SUNA」も最終的には4Kで書き出しているのですが、8Kで撮っておいてクロップするバッファをもっておくことで安心して撮影できました。
――広告写真のみならず映像業界にも需要がありそうですね。ありがとうございました!
MIRRORLIAR FILMS Season75月9日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか2週間限定上映https://mirrorliarfilms-tokai.jp/X:https://x.com/mlf_TokaiCity
記事で紹介された商品はこちら
ワンクリックアンケートにご協力ください
αUniverseの公式Facebookページに「いいね!」をすると最新記事の情報を随時お知らせします。